義肢・装具
上肢装具対策【PT専門】
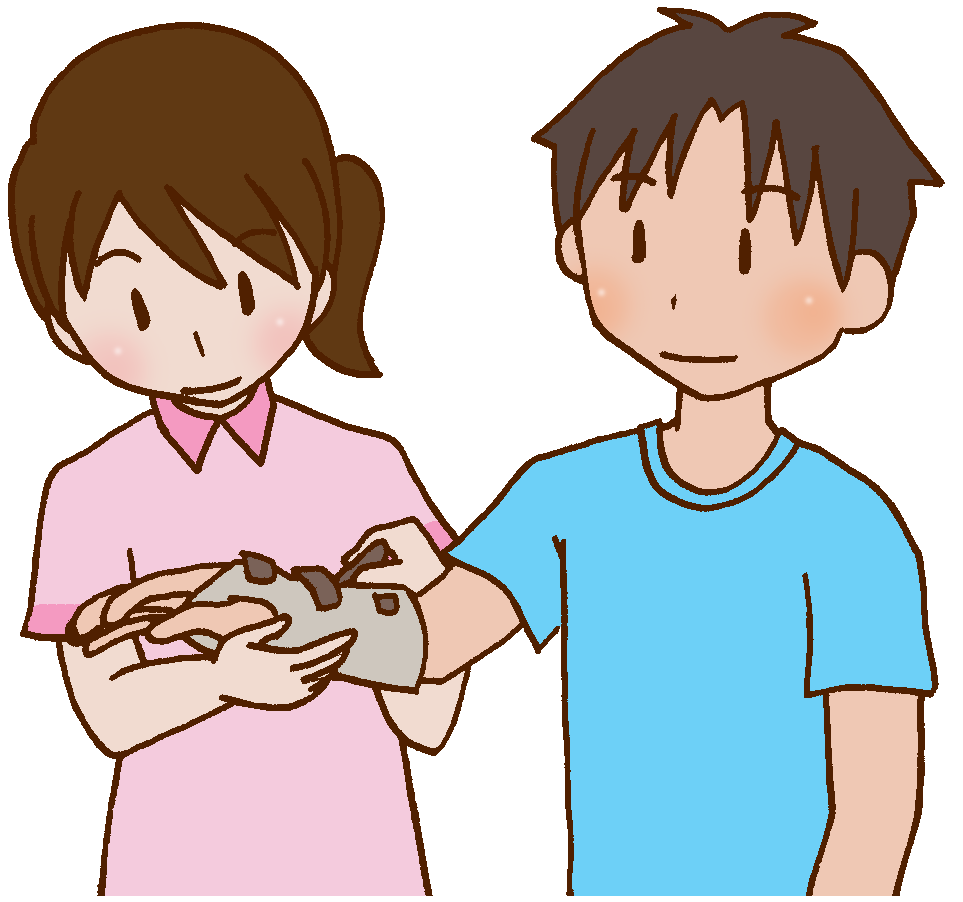
義肢・装具のジャンルは
PTでも上肢装具は度々でます。
出題傾向や頻出装具をまとめてみました!
はじめに
PT専門で上肢装具の出題率は10年で9問。
概ね年1回は
何らかの上肢装具に遭遇する計算です。
膨大な試験範囲の中でこの遭遇率は極めて高い。
対策しておいて損は無いと思います。
出現率は、PTのみだとこんな感じ。
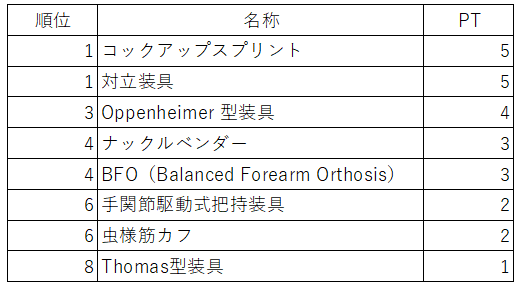
その他の装具としては、
以下も各1回ずつ出てきましたが・・・。
・IP関節伸展補助装具
・母指Z型変形用スプリント
・逆ナックルベンダー
・パンケーキ型装具
これらに関しては、余力があればで良いと思います。
PTでこれらが「正答」となる事もまず無いでしょう。
出題傾向
出題の内訳としては・3大麻痺手 5問
・装具全体 2問
・熱傷 1問
・肩手症候群 1問
やはり猿鷲下垂の3大麻痺手がメインですね。
あとは装具全般の用途を問われる問題。
Oppenheimer型装具が「Milwaukee装具」や「Williams型装具」などに紛れて登場していました。
ここ2年連続で出ています。
上記ランキング外のマイナーな装具は恐らく出ないと思います。
熱傷に関する問題にも稀に出ます。
ただ、どちらかというと「熱傷に関して」深掘りする方が良いと思います。
「熱傷」は頻出ジャンルだからです。
肩手症候群は、この疾患自体が10年中1問。
ちなみにOTですら10年で2問程度。
こちらも余力があればで良いかと思います。
出そうな所をまずは固めた方が良いでしょう。
3大麻痺手
下垂手
もちろん、橈骨神経麻痺で生じるダランとした手の事です、が意外と「下垂手」という言葉自体PTでは出ることが無い。
また背屈装具は出てくる割には「正答」となった事も無し。
正しく理解し、見極めるのが大事というコトね。
名前が少々ややこしいです。
まず、「コックアップスプリント」という名称。
「総称」として背屈装具全体を指す場合と、
「静的装具」という装具を指す場合があります。
えー・・・図にした方が分かりやすいですね。
こういう事です。
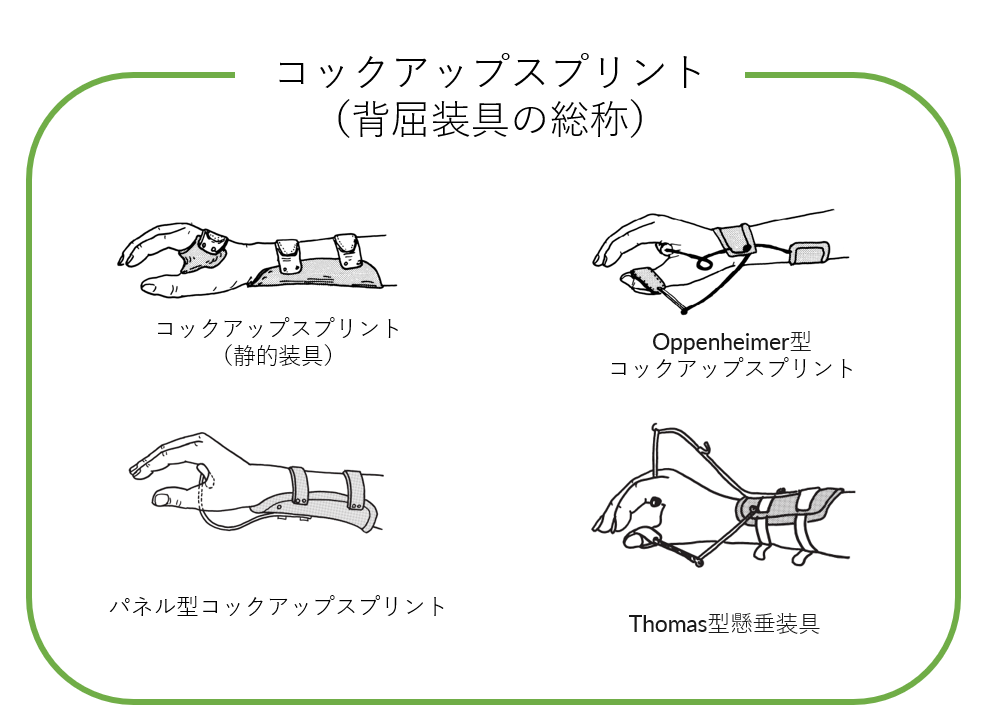
まぁ、国試的には別にどっちでも良いです。
なぜなら、これらが背屈装具だと分かれば良いからです。
「この中のどれが適応か」等とはOTですら問われません。
学習の際に混乱しないように念のため書いておきます。
見た目に関しては、当然、背屈している事が特徴なのと、
母指外転を補助しようとしている点で見分けましょう。
特に困るのがオッペンハイマーとトーマス。
全然名前からモノが想像できないタイプですね・・・。
トーマスはPTでは絵も出た事ないですがこんな装具で、
この「上に突き出した懸垂具」が最大の特徴です。
この辺がなんか「きかんしゃトーマス」っぽい(?)ので、
なんとかそれで覚えて下さい。
 ほらっ。煙突っぽいっ。
ほらっ。煙突っぽいっ。
なのでこれをもってトーマスとしましょうね!
 ね!
ね!
あと、
オッペンハイマーは・・・うーん。
トーマスからの・・・
トップハムハット卿
オップハンハット
オッペンハンマット
オッペンハイマー
オッペンハイマー!!
・・・すみません。
良い覚え方あれば教えてください。
次いきます。
猿手
はい、正中神経麻痺ですね。特に母指球の筋萎縮による対立障害がターゲットです。
こちらの装具は、名前に関しては、「対立」とついてくれているので安心。
いくつか種類がありますが、「対立」とついていればOKです。
OTでは長対立装具と短対立装具の見極めが必要ですがPTでそこまでは不要でしょう。
(ちなみに、内在筋のみの麻痺なら「短」、外在筋の麻痺もあるなら「長」です。)
Rancho型とかについても無視で大丈夫。
これも、OT専門問題でも見分けてませんから。
見た目に関しては、母指を外側から包み込んでいる感じ。
長対立装具だとこうで、
(ちなみにコレがRancho型ですが、そこはどうでも良いです)
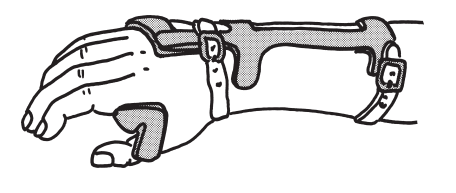
短対立装具だとこう。
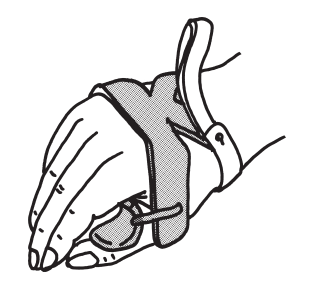 母指を対立位に持っていこうと外側から押さえつけていますね。※
母指を対立位に持っていこうと外側から押さえつけていますね。※
例えば、先ほど出てきたOppenheimer型装具と比べてみると一目瞭然。
 こちらは橈骨神経(母指外転筋)麻痺を補助するために外側に引っ張っています。
こちらは橈骨神経(母指外転筋)麻痺を補助するために外側に引っ張っています。
※「母指を外側から押さえつける」だけだと手関節駆動型把持装具もそうなるんだけど、それはまた後述します。
鷲手
続いて、尺骨神経麻痺の「鷲手」。
頻出はこの2つ「ナックルベンダー」と「虫様筋カフ」
・・・ですが、
ややこしいよなぁ。
虫様筋って尺骨・正中神経の両側支配なのに
名前的には尺骨神経麻痺にだけ適応なの?みたいな。
すみません、今の所特に良い覚え方は無いので根性でお願いします。
「虫様筋カフ」は、鷲手の尺骨神経麻痺です。
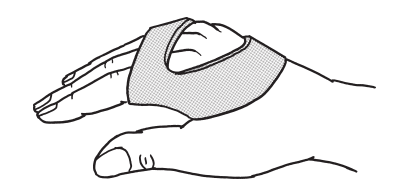
ちなみに、ナックルベンダーと虫様筋カフは、同じ用途で静的と動的の関係にあります。
静的だと良肢位の保持や、特定の手の形での機能の向上ができます。
動的なら手の動きを大きく阻害せず、目的の機能を補助できます。
この辺の見極めも問われる事はありませんが、
対象的な物をセットで覚えると印象に残りやすいですよ。
こちらがナックルベンダー。
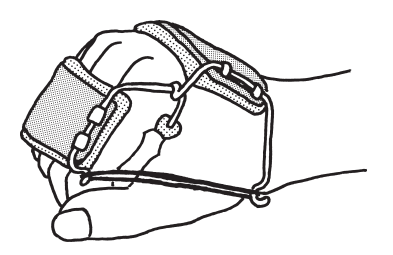
ナックルベンダーというのもよく分からんので調べてみた。
ナックルとは拳骨とか握りこぶしに関連する意味合いがある。
野球でもナックルボールという変化球がありますね。
由来は諸説あるが1つには「曲げた指の第1関節(Knuckle)部分でボールを握り、突き出すように投げる」からだという。
やはり握る事に関連するのだ。
ともかく、握らせようとしてくるタイプが「鷲手」適応です。
その他の装具
ランクインしている頻出装具だと、「BFO」と「手関節駆動式把持装具」ですね。
どちらも主な用途は頸髄損傷。
頸髄損傷に関連する問題では起き上がりや移動など、PTらしい問題がいくらでもあります。
頸髄損傷に関する上肢装具の問題は今の所なく、今後もほぼ出ないと思われます。
一応、選択肢に出た時に迷わない様に解説しておきます。
BFO
BFOとはBalanced Forearm Orthosisの略。問題はいつも「BFO」とだけしか記載されていないのだ。
知らないと全く意味不明。
こんなやつです。
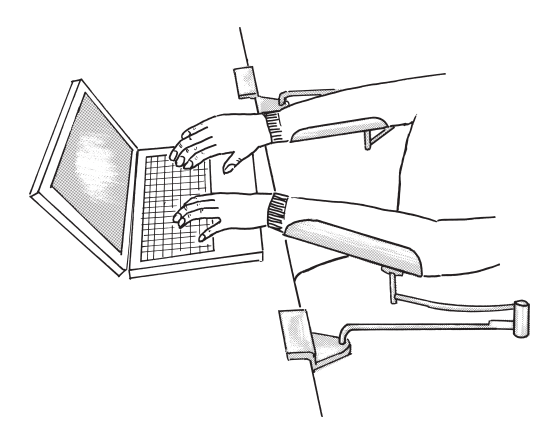
C4~C5Aの頚髄損傷で適用です。
前腕で腕全体をがっつり支えている、重度者用の装具ですね。
手関節駆動式把持装具
パッと見は長対立装具みたいな感じ。
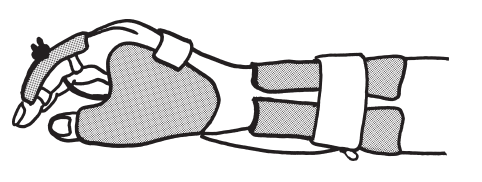
実際、対立位になるように作られています。
C6レベルが適応であり、そのレベルだと対立筋ふくむ内在筋が効かないからでしょう。
大きな違いは手関節部が、名前の通り駆動する仕組み。
この手関節の動きを利用してテノデーシスアクションによる把持を補助するわけです。
色んな型がありますが、こちらもOTですら問われませんが・・・。
見た目の判断材料として何種類か並べておきます。
名前は覚えなくて良いので記載もしません。
大事なのは、どれも「手関節駆動式把持装具」だということ。
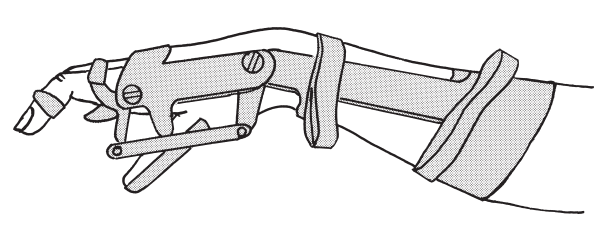

以上です★
上記2点は頚損用の装具だと思ってもらえれば良いですし、最初にも書きましたがPTで頚損の上肢装具が問われる事は無いでしょう。
まとめ
- 頻出の装具を押さえておこう。
- 同じ機能の装具だと分かれば良い。
- 名前と見た目と用途を結び付けておきましょう。
上肢関連は苦手という方も是非、頻出だけは押さえておきましょう。
年1ペースと、本当によく出ます。
名前・見た目・用途の結び付けはもちろんですが、
ポイントはPTの国試で問われるレベルです。
細かな違いまで完璧にしなくても良いのです。
同じ機能の装具だと分かれば大丈夫!
◆参考文献
knuckleとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典